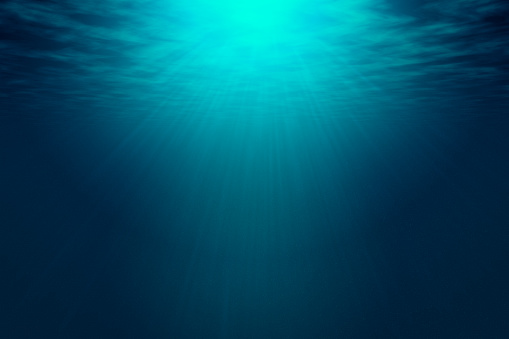2018年/アメリカ
ギレルモ・デル・トロ監督らしいダークファンタジーの世界観を構築しながらも、しっかりとテーマを描いている作品ですね。
ヴェネツィア映画祭で金獅子賞獲ったことを皮切りに、ゴールデングローブ賞、アカデミー賞と総なめにしたのも肯けます。
テーマは題名が示しています。
シェイプ・オブ・ウォーター。つまり水の形という意味ですね。
人の気持ち、人と人との関係、人と生物との関係は、水の肩のようにどうにでも変化をするし、切ってもきれないモノだということでしょう。
そしてこのテーマを語るためにまず主要登場人物のすべてを孤独なマイノリティに設定したのは、なかなか秀逸なやりかただと思います。
発話障害を持つ主人公のイライザ、アパートの隣人であるゲイのジャイルズ、同僚で、夫と距離を感じて生活しているアフリカ系女性のゼルダ、そして実はソ連のスパイであるホフステトラー博士。
結果的に半魚人と呼べる生物を救い出そうとした四人は、みな孤独を感じながら生きている人たちです。
だからこそ、捕らえられて隔離されている孤独な半魚人に共鳴していき、半魚人も自分たちと変わらない生き物なんだということに気がついていきます。
イライザが半魚人を助け出そうとジャイルズを説得する際に言っていた、彼(半魚人)だけは喋れないわたしに偏見を持つこともなく受け入れてくれているといったニュアンスの言葉が印象的でした。
それはそうですよね、イライザにとっては人間は同族であっても、ほとんどの人間はイライザを欠けたものがある不完全なものという色眼鏡でしか見ない。
むしろ半魚人の方がイライザを尊重して接しているわけですからね。
一方でこの孤独なマイノリティたちに対する役どころであるストリックランドのバックグラウンドの描き方も面白いです。
1960年代にあって、差別意識丸出しの白人男性。
彼は当時の富の象徴である、美人の奥さんや二人の子供、それにキャデラックと持てるものを持っている人物です。
つまり孤独なマイノリティたちと見事なまでに線対象として描かれています。
でも、その持てる男であるストリックランドの方が半魚人が行方不明になってからは精神的に追い詰められていく。
この二項対立は非常に巧みですね。
力と豊かさの只中にあるはずの男が実は男社会の中の縦の関係で雁字搦めになっており、自分の地位を守るために絶えず焦らなければならない。
物語がどんどんと進んでいくに従って孤独なマイノリティと対局の立場にいたはずのストリックランドも孤独であり、もっと言えば孤独であることに気がついてすらいないということが暴露されていくんですね。
物語の終盤では、怪物であるはずの半魚人の方がまともに見え、一方で神に近い人間とされる立場にいるはずのストリックランドの方が怪物に見えてくるという逆転現象が、観る人にとっての印象として残っていきます。これは「第9地区」などでも採られたやり方ですけれど、ある意味確立されつつある一つの手法ですね。
確かにこのやり方で観ている側の価値観を逆転させれば、不思議なことに自然とテーマがストンと腑に落ちていくんですよね。
それにしてもギレルモ・デル・トロ監督の世界観の描き方は面白いです。
実際によくよく考えると、ツッコミを入れたくなるような箇所はあちらこちらにもあるんですが、それをすべて含めての彼の世界観の描き方なんですよね。
つまり、すべてのリアリティに仕上げるのではなく、細部にあえて隙間を作る。
その隙間のおかげで、物語そのものがリアルなものなのか幻想的なものなのかわからなくなり、結果的に観ている人に判断を委ねていくことで、彼独自の世界観が保管されていくんですよね。
これは一歩間違えれば、B級映画になりかねないところを、彼なりの独特のセンスによって絶妙なところで現実とファンタジーの間にラインを引いているんです。
真似できないやり方ですね。でも、このやり方で彼は毎回観ている人を彼独自の空間に引き込んでいくんです。
この映画では、特に緑にこだわった色づかいと水の流動性を非常にうまく使っているなという印象を持ちました。
やはり次の作品も気になってしまう監督ですね。